こんにちは。
今回から特殊奏法を用いた曲を弾いていきましょう。
...と言いたい所ですが...
まずは特殊奏法をする為に必要な"変則チューニング"の説明をさせてください。

さて、今までは"レギュラーチューニング"というものに合わせてギターを弾いてきましたね。
この基本的なレギュラーチューニングに合わせる事で、
決まったコードフォームで弾けたり、楽譜を読んだり出来るんでしたね。
当然ですが、このレギュラーチューニングから変更すると言うことは、
今まで覚えたコードフォームやフレット構造がまるっきり使えなくなると言うことです。


変則チューニングをするメリットは色々とあります。
その中でも一番のメリットは"開放弦を有効に使える"事だと考えます。
変則チューニングの実例を挙げて一緒に考えてみましょう。
今回取り上げるのは、"Open.Dチューニング"です。
Open.D Tuning
1.D
2.A
3.F#
4.D
5.A
6.D
このチューニング全体的に"D"が多くないですか?
そして、"A"と"F#"ですね。
コードの構成音がしっかり頭に入ってる方はお気付きかと思います。
開放弦が全てDコードの構成音なのです。
つまり何も押さえず開放弦を弾くとそれがそのままDコードになると言うことです。
Open.D とは、Open = 開放弦 D = Dコード という意味ですね!!
とても便利そうですよね。


例えば、Open.Dチューニングの状態でkey.Dの曲を弾くとしましょう。
基本的に使える音は、"Dメジャースケール(D・E・F#・G・A・B・C#)"ですね。
まずはOpen.Dチューニングでのフレットの状態を確認してみましょう。
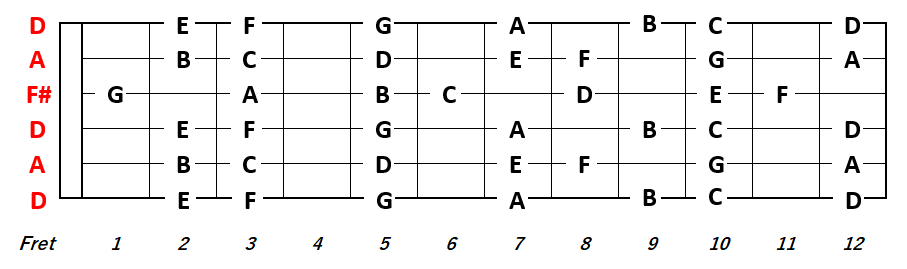
開放弦の音が全てスケール音になってますね。
つまり6弦全ての開放弦が曲の中で使える音という事になります。
これはとても便利です。
開放弦を織り交ぜた音が大きく跳ぶようなフレージング
開放弦を組み合わせた音幅の広いコードフォーム
その他にも様々な活用法があります。


例えば、key.EであればOpen.DにCapo.2で対応します。
変則チューニングの概要としては次のように認識してください。
もちろん細かく見ると様々な特徴がありますが、
大まかには"曲と相性の良いチューニングをすることだ"と考えて下さい。
変則チューニングとは...
曲のKeyに合わせて行うチューニングである。
開放弦がKeyに合ったスケール音になる。
あとは次回以降、実際に弾きながら特徴を見ていくことにしましょう。
是非、楽しみにしていてくださいね。
それでは、今回の講座は以上になります。
ありがとうございました。
NEXT
-

-
例え話で音楽を理解し自在に音を操るギター初心者講座【特殊編(3)】 -演奏解説-
【特殊編】-講座(3)- 特殊奏法の解説です。4つの基本パターンを基に両手の使い方と各手の役割について理解しましょう。
TOP
-

-
例え話で音楽を理解し自在に音を操るギター初心者講座【特殊編】
例え話で音楽を理解し自在に音を操るギター初心者講座【特殊編】まとめページです。(全5講座)